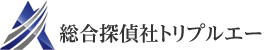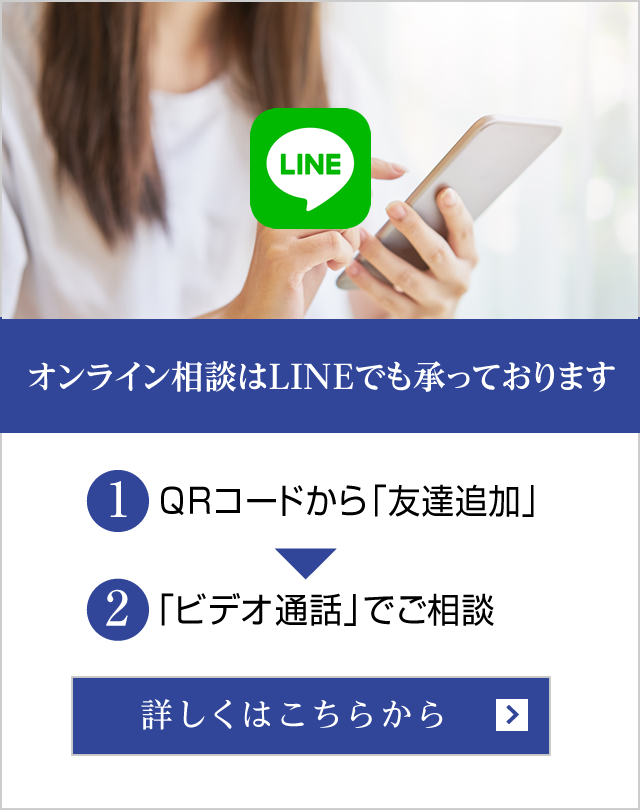脅迫を受けたとき、恐怖や不安でどうすればいいか分からず、冷静な判断ができなくなるのは仕方のないことかもしれません。
しかし、そのような状況につけこまれて不当な要求をされたり、金品を巻き上げられるなどの被害は避けたいものです。
この記事では、脅された時に取るべき初期対応や証拠の残し方、さらに法的手段や相談窓口の利用方法を詳しく解説します。
あなたの不安を少しでも軽くし、冷静に問題を解決するための具体的なステップをお伝えします。
目次
脅された時の初期対応
脅されたとき、多くの人は恐怖と不安に襲われ、冷静な行動がとりにくいものですが、適切な初期対応を取ることで、問題を最小限に抑えることができるでしょう。具体的なポイントを解説します。
冷静な判断をする
脅迫を受けた場合、恐怖や怒りに支配されることなく、冷静さを保つことが何よりも重要になります。
特に相手と対峙している場合などは状況を見極める事が必要で、まずは自分の身の安全を確保することを考えましょう。
その後、落ち着いた状況下で考えることができる状態になった際には、以下のようなことを確認してください。
- 具体的な脅迫の内容を把握する
- 相手の身元が分かる場合は確認する
- 内容に緊急性があるかを判断する
- 同様の被害が他にないかを調べる
- 自分の情報が漏洩してないか確認する
証拠を確保する
脅迫への対処で重要なのが証拠の確保です。これらの証拠がない場合、警察や弁護士も動きづらくなるため、次のような方法で証拠を確保しておきましょう。
スクリーンショットの保存
LINE・メール・SNSのメッセージは、消される可能性があるため、スクリーンショットを撮影して保存しておきます。撮影した日時を記録しておくとさらに効果的です。
録音・録画
直接会話や電話での脅しがあった場合、可能であれば録音や録画を行いましょう。相手に知られずに行う必要がありますが、法的に有効な証拠となる場合があります。
バックアップの作成
証拠データは複数箇所に保管し、第三者にも共有しておくと安全です。
相手とは直接対峙しないメリット
脅しを受けた際、相手に直接対峙することは避けるべきです。怒りや恐怖心から反論したり、挑発的な言葉を返してしまうと、相手をさらに刺激し、状況を悪化させる危険性が高まってしまうでしょう。
例えば、感情的に言い返せしてしまった場合、相手との口論に発展して暴力沙汰になる可能性もあり得ます。相手と対峙することはできるだけ避け冷静に距離を置くことが重要です。
周囲に相談しサポートを得る
一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人に相談することが大切です。他者に話すことで状況を客観的に見つめることもでき、不安を軽減する効果も期待できます。
また、職場や学校で発生したトラブルであれば、上司や信頼できる教職員に相談することです。問題解決の糸口が見つかる可能性も高まるでしょう。
必要に応じて専門家に相談をする
脅迫の内容が深刻な場合は、弁護士や警察などの専門家に相談することを検討しましょう。専門家に相談するメリットや具体的な方法については、後のセクションで詳しくご紹介していますので、併せてご確認ください。
家族を巻き込んだ脅迫への対応
脅迫の中には、家族を巻き込む形で行われるものも少なくありません。相手が「家族に危害を加える」などと脅してきた場合が挙げられます。
家族の安全を守るための、具体的な対策を紹介します。
家族の安全を守るためにすべきこと
最優先すべきは、家族の安全を確保することです。以下のような対応を速やかに行いましょう。
家族に状況を説明し警戒を促す
家族には危険性をしっかり伝えましょう。「変わった車が家の周りをうろついている」「不審な電話がかかってきた」といった具体的な兆候がもしあれば、ただちに共有し、家族全員で警戒する必要があります。
住居のセキュリティを強化する
- 鍵の交換
- 防犯カメラの設置
- センサーライトの導入
物理的な安全対策を講じることで、家族全員の安心感が高まります。また、郵便物やゴミに個人情報が含まれないように注意しましょう。
子どもがいる場合の注意ポイント
学校への送迎を強化する、知らない人について行かないよう注意を促すなど、子どもが危険にさらされない環境作りをしましょう。
家族への情報共有と協力の依頼
家族の安全を守るためには、全員が同じ情報を持ち、協力して行動することが不可欠です。
脅迫内容を共有する
脅迫がどのような内容で、どの程度現実的な危険性があるのかを家族に説明します。家族の行動が統一され、無駄な不安を煽らずに、冷静な対応が取れるようになります。
家族間の連絡手段を確保する
緊急時に迅速に連絡が取れるよう、携帯電話やチャットアプリで、常に連絡を取り合う体制を整えておきます。
役割分担の決定
誰が警察に連絡をするのか、誰が子どもの送り迎えを担当するのかなど、家族全員で役割を決めておくと、いざという時にスムーズです。
家族の行動範囲や生活パターンの見直し
相手に行動を把握されないよう、普段の生活パターンを変更することが有効です。
通勤・通学ルートの変更
日常的に利用するルートを変えることで、相手が居場所を突き止めるリスクを軽減できます。複数のルートを用意し、日によって使い分けるようにしましょう。
SNSでの発信内容を見直す
住所や生活パターンが特定される可能性のある投稿は避け、家族全員がプライバシー設定を厳しくするように依頼します。
一時的な避難を検討する
危険が高いと判断した場合は、短期間でも信頼できる友人や親族の家、または安全なホテルに避難することも検討します。状況によっては、警察の協力を得て身の安全を確保しましょう。
脅迫罪とは?具体的な事例
脅迫罪は、刑法第222条に定められた犯罪で、人の意思の自由を脅かす行為を処罰するものです。
ここで重要なのは、脅迫の内容が「害悪の告知」に該当するかどうかです。害悪とは、被害者またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えることを指します。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
脅迫罪に該当する言葉
例えば、次のような言葉が脅迫罪に該当する可能性があります。
- 生命への害悪告知:「お前を殺す」「親の命を狙っている」
- 身体への害悪告知:「殴るぞ」「夜道には気をつけろ」
- 自由への害悪告知:「ここから逃がさない」「子どもを誘拐する」
- 名誉への害悪告知:「秘密を暴露する」「写真をネットに公開する」
- 財産への害悪告知:「車を壊してやる」「ペットを殺す」
これらの言葉は、直接的な危害を伝える内容であれば、相手が恐怖を感じるかどうかにかかわらず脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の背景にある動機
脅迫行為が行われる背景には、さまざまな動機が存在します。
金銭トラブル
借金の取り立てやお金の貸し借りに関連して、「金を返さないなら痛い目に遭わせる」といった発言がされるケースがあります。
人間関係のトラブル
友人関係や職場でのトラブルにおいて、「秘密を暴露する」「評判を落とす」と脅すことで相手を支配しようとするケースが見られます。
恋愛関係のもつれ
別れ話や不倫が発端となり、「家族にばらす」「職場に不倫の事実を知らせる」といった言葉が使われることがあります。
SNSやインターネットのトラブル
匿名性の高いネット上では、コメントやメッセージを通じて「殺害予告」「嫌がらせ」をするケースも見受けられます。
こうした背景を理解することが、脅迫行為の防止や早期対応に役立ちます。
脅迫罪の具体的な事例
AさんとBさんは同じ職場の同僚でしたが、些細なトラブルがきっかけで関係が悪化しました。ある日、AさんはBさんに対し、「お前が会社の経費を私的に使っている証拠がある。バラされたくなければ、俺の言うことを聞け」という内容のメッセージを送りました。
Bさんは事実無根の内容にもかかわらず、周囲に誤解されることを恐れ、Aさんの指示に従わざるを得ない状況に追い込まれました。このように、相手の評判を落とすことをほのめかし、恐怖を与えて支配しようとする行為は脅迫罪(刑法222条)に該当します。
実際に情報を暴露しなくても、「秘密を暴く」と脅すだけで犯罪と見なされる可能性があります。
法的手段と相談窓口の活用
脅迫を受けた際には、法的な対応が必要になることが少なくありません。
警察・弁護士・無料利用できる相談窓口について具体的に解説します。
警察に相談する流れ
警察への相談は非常に重要です。特に脅迫がエスカレートする可能性がある場合、早めの対応が必要です。
以下、警察に相談する際の一般的な流れです。
1.証拠の準備
脅迫の証拠となるメッセージや録音データ、スクリーンショットを保存します。警察が状況を把握し、具体的な対応を取るための重要な資料になります。
2.最寄りの警察署に相談
最寄りの警察署に出向き、状況を詳しく説明します。「生活安全課」などの担当部署が対応してくれることが多いです。脅迫内容が重大であれば、すぐに被害届を提出するよう促されます。
3.被害届の提出
被害届は警察が事件として捜査をする為に必要です。被害届を出すことで、加害者に然るべき刑事責任を負わせるなど適切な処罰が与えられる可能性が高まります。
なお、証拠の収集が難しい場合は、探偵の活用も有効です。探偵は、脅迫を裏付ける証拠を合法的かつ専門的に収集するスキルを持っています。
加害者の身元特定や詳細な調査が必要な場合、探偵の調査報告書は警察や弁護士にとって信頼性の高い資料として役立ちます。
弁護士に相談するメリット
弁護士への相談は、脅迫への対応において大きな力になります。
法的助言の提供
脅迫がどの法律に抵触しているか、どのような手続きが必要かについて、具体的なアドバイスが得られます。
加害者との交渉代行
弁護士が加害者との交渉を代行することで、被害者自身が直接関与するストレスを軽減できます。
訴訟の準備とサポート
万が一、訴訟が必要になった場合でも、弁護士が必要な書類の準備や法廷での対応を行ってくれます。
無料相談の活用方法
弁護士に相談するハードルが高い場合は、無料で利用できる相談窓口があります。代表的なのが、法テラス(日本司法支援センター)です。
法テラスの活用ポイント
無料の法律相談
法テラスでは、収入に応じて弁護士や司法書士との法律相談を無料で受けられる制度があります。脅迫の状況を説明し、最適な解決策を提案してもらえるでしょう。
全国対応の窓口
法テラスは全国各地に窓口を設けており、電話やオンラインでも相談が可能です。特に地方在住で弁護士との接触が難しい方にとっては心強い支援となります。
法テラスサポートダイヤル:0570-078374(おなやみなし)
出典元:法テラス
脅迫を防ぐための予防策
脅迫は、日頃から適切な予防策を講じることで、リスクを減らすことが可能となります。具体的な予防方法について解説します。
SNSでの情報管理
SNSが脅迫の発端になるケースがあります。ポイントを押さえて情報管理を徹底しましょう。
個人情報の投稿を控える
本名・住所・電話番号などの個人情報は、SNS上で公開しないようにしましょう。
定期的なパスワード変更
長期間同じパスワードを使用するのは危険です。英数字や記号を組み合わせた複雑なパスワードに定期的に変更することで、アカウントの乗っ取りを防ぎます。
知らない人との接触を最小限にする
SNS上での見知らぬ相手とのやり取りや、過剰な親密さを見せるのは避けましょう。最初からプライベートな話題に踏み込んでくる相手には警戒が必要です。
個人情報の公開範囲を見直す
個人情報は、意外な場所から漏洩することがあります。以下の行動を取り入れることで、情報漏洩を防ぎましょう。
SNSや通販サイトなど、利用しているサービスのプライバシーポリシーを見直し、どのような情報が収集され、第三者に共有される可能性があるかを把握しておきます。
トラブルの兆候を早期に察知する
トラブルは、予兆を見逃さないことで早期に対処できます。以下の行動が役立ちます。
威圧的な発言や過剰な干渉、金銭を要求するようなメッセージが見られる場合、トラブルの前兆である可能性があります。その場で解決しようとせず、信頼できる第三者に相談しましょう。
自分の過去の経験を振り返り、似たような兆候がないか確認することも有効です。同じ失敗を繰り返さないために、警戒心を高めましょう。
まとめ
脅された際の対応は、冷静さを保ちつつ適切な行動を取ることが鍵となります。証拠を確保して周囲に相談し、必要に応じて専門家の力を借りることで、安全かつ法的に問題を解決する道筋が開けます。
また、日頃からSNSの情報管理や生活パターンの見直しを徹底し、脅迫のリスクを未然に防ぐことも重要です。一人で抱え込まず、家族や信頼できる人々と協力しながら行動することで、不安を軽減し、自分や家族を守ることができるでしょう。